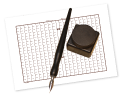アマゾンでナマケモノに出会う
(1)ようやくパニャコチャ生態系保護区の入り口に達した。そこにある原住民の村に寄る。ガイドのランディが舟を降りて住民の男たちと話し込んでいる間に、先ほど追いこしたばかりの小さなカヌーが、追いつき、そのまま通り過ぎてゆく。岸の男たちから声がかかるが、それを無視して男はカヌーを漕ぎ続ける。
また走り出した我々のモーター・ボートがそのカヌーに追いつくのに時間はかからない。ランディは舟をカヌーに近づけるよう指示して、一緒に乗っていくようにと男を誘った。
粗末な服を着たその男はこの先に住むシャーマンだった。カヌーをロープで繋ぎ、男を乗せて、ぼくたちの舟はまた走り出す。ぼくのすぐ隣に座った彼は嬉しそうな、しかし少し恥じらうような笑みを浮かべて時々ぼくの方を見る。つやつやした銅色の顔、口のまわりにまばらに生えている柔らかなヒゲ。ぼくは何かを言ってその笑みに答えたいと思いながら、適当なことばが見当たらず、やはり曖昧な笑みを返すばかりだ。そのうちに前に座ったランディが、ぼくたちのツアーについてあれこれ説明してくれた。シャーマンはそれにいちいち相づちをうつ。
「うんうん、それはいい」とシャーマン。
「地球のちょうど裏側だよ」とランディ。
「うん、それはいい」
「ヤマハ・モーターの国だ」
「うん、それはいい」
こんな調子だから、ランディの話題もすぐに底をついてしまう。するとその後にまたぼくとシャーマンの微笑みに満ちた沈黙が続く。
しかし、やがて、どうしてそんなことを言う気になったものか、ぼくはシャーマンに「ぼくはナマケモノという動物が好きなんです」と言った。すると彼は一層嬉しげに顔をくずし、「うん、それはいい」と言って、まるでそこにナマケモノがいるとでもいうように岸辺の木々の梢を見上げた。
彼の家に着く。颯爽と岸に降り立つと、彼は我々に待っているようにと告げて、高床式の家へとスロープを駆け上がった。やがて川辺に戻った彼の手の中には燻製のピラニアが五、六枚。これをぜひ客人たちに食べてもらってくれとランディに言う。そしてもう一度家にとって返したシャーマンは今度は両手にいっぱいの真っ赤なトウガラシをもってきてぼくたちにくれた。そしてこう言った。「明日、あんた方に会いに行くよ。じゃあ、その時にまた」。舟が見えなくなるまで彼は川辺に立ってぼくたちを見送った。
(2)パニャコチャ湖に着いたぼくたちは、早速、湖の主である川イルカ(ピンク・ドルフィン)の出迎えを受ける。シャーマンの祝福は受けるわ、イルカの歓迎は受けるわ、君たちは幸運だね、とランディ。長旅を終えロッジに到着。オリエンテーションを受け、それぞれの小屋に荷物を運びこんだぼくたちは、休む間もなくランディに誘われるまま、湖に泳ぎに行った。
湖の名がパニャコチャ(ピラニアの湖)であることもしばし忘れて、ぼくたちはカヌーから次々に夕暮れの湖水へと勢いよく飛び込んだ。西へ傾いた日が湖面に金色に染めている。ランディに言われて、水の中に潜って耳を澄ますと、「キチキチキチ・・・」という音がしきりにする。これはある種の魚のたてる音だという。
しばらく一心に泳いでいると、カヌーの上から誰かが「あっ!三本」と叫んだ。皆、西の空を見る。するとちょうど太陽が雲の後ろから、斜め上方に長く鮮やかな三筋の桃色の光を発している。カヌーの上にいる者も、水の中にいる者も、しばしその美しさに見とれていた。三本の光。ぼくはもちろん、この湖を取り囲む森の主であるミツユビナマケモノのことを考えていた。そして、今ぼくと同じ水の中を泳いでいるはずのピンク・ドルフィンたちのこと。
(3)アマゾンに夜のとばりが降りる頃、雨が降り始める。そして朝方には雨脚が強まったが、朝食の頃にはひとまず止み、かすかに陽も差し始めた。一番奥に位置しているぼくの小屋へ誰かが息を切らせてやってきて、ドアの向こうから「先生、大変です。ナマケモノがいます」と叫んだ。ぼくは早速、カメラや三脚をかついで、母屋の方へと向かう。
そのミツユビナマケモノはなんと母屋の斜め前にあるパパイヤの幹につかまっていた。雨が止むのを待って、大きな木から降りてきて、このパパイヤの小木にのり移ったという。これまでナマケモノがロッジの周辺に現れることはあっても、こんな風にロッジの庭の木に出現したことはなかった、とここに住み込んでいる管理人の若者は驚いている。まるで、わざわざ君たちに挨拶するためにやってきたみたいだね、とランディも半ばあきれ顔だ。
彼の指示で誰かが椅子を一脚もってきてパパイヤの木の下に置く。ぼくたちはひとりひとりその上にのって手を伸ばし、遠慮がちにナマケモノのフサフサとした背中を撫でたり、後ろ脚のミツユビならぬ「ミツヅメ」に触れたりした。その間もナマケモノは全く動じる気配はなく、目を閉じたり、またうっすらと開けたり、夢とうつつの間を行ったり来たりしているようだった。
その日のツアーのための準備をするために小屋に一度戻り、また数十分後に行ってみると、もうパパイヤの木にもその周辺にもナマケモノの姿はなく、まるでつい先ほどの出来事が嘘のようだった。
(4)その日も次の日も、シャーマンは来なかった。ランディによると、ああしてシャーマンが訪問者に対して自らすすんで「会いに行くよ」などと言うこと自体、珍しいのだそうだ。楽しみにしていたぼくはがっかりしたが、まあ、あのパパイヤの木のナマケモノはシャーマンが自分の代わりに送ってくれた使者だったかもしれないな、と考えて納得することにした。それにしても彼にもらった燻製ピラニアはうまかった。骨が多くて肉は少なかったが、味はよく、魚というよりは鶏のような歯ごたえだった。
出発の朝、パッキングをしてそれぞれの小屋から荷物を母屋に持ち込み、ぼくたちは最後の食事の席に着こうとしていた。そこへシャーマンが現れた。彼は例の微笑みを浮かべてぼくたちに挨拶した。今日の彼は穴の開いていないシャツを着こみこざっぱりしてみえた。ランディがぼくに耳打ちする。「せっかくだから、出発の時間を少し遅らせて、食事の後、シャーマンを囲んでミーティングをやろう」
期待通りのすばらしい会合になった。キチュア語を話す先住民ガイドのラミーロが通訳をしてくれた。ぼくたちの質問にランディは時にひやひやしたらしいが、シャーマンは終始おだやかに、しかし真摯に答えてくれた。ジャガーをはじめとした森の動物たちの精霊と交信する話。パニャコチャ湖の湖底にある町の話。その町の主である長いヒゲの小人の話・・・。川イルカについて、シャーマンはこう言った。「みんな、イルカは動物だとか魚だとかと思っているけど、ほんとは人間なのさ。じゃあ、我々人間とどこが違うかって? 違うのはただ、彼らの方がより優れた人間だという点だけさ」
ぼくは最後に、一番聞きたかったことを尋ねた。「じゃあ、ナマケモノというのはあなたにとってどんな動物ですか」。早速彼はまたあの上方を見つめるような目つきになって答えた。「うん、とてもいい動物だ。いつも静かに、誰に迷惑をかけることもなく、ゆっくりあわてずに、誰とも争うことなく、のんびりと生きている」。幸せな気分に浸りながら、ぼくはもうひとつ、「ナマケモノのことをあなた方のことばでなんと言うんですか」ときいた。
よくぞきいてくれました、とまでは思わなかったかもしれないが、シャーマンは確かにとても嬉しそうに微笑んで答えた。「インティジャーマ」。インティは太陽、ジャーマは光線。その時、あの夕暮れの湖で見た三本の光線や、雨上がりの後に現れた使者の姿を、心の中にくっきりと思い描いたのは、ぼくだけではなかったはずだ。